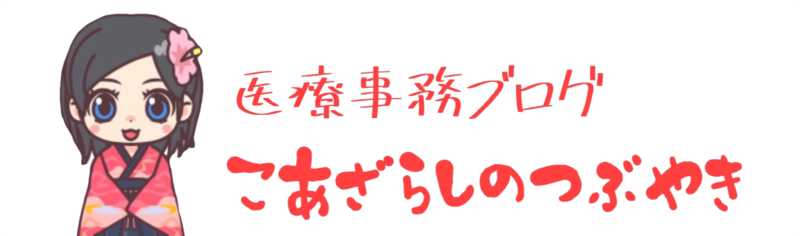本ページには広告を含むリンクがあります。
質問回答|レセプトで傷病名診療開始日の更新するしないは年齢によって変わるのですか?

こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。
読者の方からレセプトの算定について質問がありましたので、回答をシェアします。
目次
[質問]レセプトで傷病名診療開始日の更新するしないは年齢によって変わるのですか?
 質問者さま
質問者さま傷病名の診療開始日についてですが、結膜炎、咽頭痛、便秘、胃炎、頭痛など、老人の場合は開始日が古くても大丈夫で、65歳以下は当月傷病名に更新が必要だと先輩からお聞きしました。



そうなんですね。



しかし、例えば結膜炎なんですけど、アレルギー性による結膜炎であれば、患者のアレルギーから発症するものだから、診療開始日は発症日となりますが、通常の結膜炎は、一過性のものであるから、処方されたら当月開始日でないといけないと思うのですがどうなのでしょうか?
こあざらしの回答
小児や高齢者というのは免疫機能が弱いということもあり、疾患が長期化することが多いという見解があります。
一律何歳からといった線引きはなく、傷病名の開始日は患者ごとで状態が異なり、状況に応じて医師に判断されるべきものです。
例えば、アレルギー性結膜炎、アレルギー性鼻炎といったものは繰り返しなりやすく、また、季節に左右されるものもあれば通年のものもあります。



それは患者さん自身が実際にどれに該当するかによって発症日の概念は変わってくるのではないでしょうか?
季節性であれば一過性のものなので、初診となるかもしれませんし、慢性的症状を示しているということであれば通年性と判断でき再診として継続となるかもしれません。
初診料が査定されるから発症日を変えるのではなく、正しい発症日で記載されるべき部分です。
医師が初診のものと判断すれば病名の開始日は当月でなければならないと思いますし、継続の症状と判断されるのであれば病名は以前よりあるもので記載することとなり、それは再診料で算定します。
初診料、再診料の算定を決めてからの病名開始日ではなく、病名の発症日を決めてから初診料になるのか再診料になるのか判断するという感じです。
診察をしている医師が判断出来るものであり、事務員で勝手な判断は出来ません。



65歳という年齢で分ける指示が出ているのであれば、書面審査としての線引きではないでしょうか?
65歳と言えば退職年齢の節目でもあることから、健康保険が切り替わり、社保から国保に変わるため審査機関の審査差異から生まれた解釈かもしれませんね。
あわせて読みたい




低薬価薬剤のレセプト請求、傷病名記載が必要な投薬の基準は?
こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。 今日は薬剤の請求についてお話しようと思います。レセプト請求における原点に返る話ですが、知っておくとレセプト業務の...
あわせて読みたい




質問回答|ウリトス錠の査定理由が分かりません。「~に伴う」病名のレセプト記載方法は?
こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。 今回、ウリトス錠の査定について質問がありました。 [質問]ウリトス錠の査定理由が分かりません。「~に伴う」病名の...